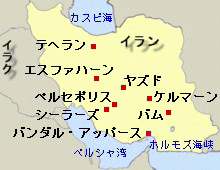
なんだか恥ずかしい事をしてしまったような戸惑いを感じて、手に握った250リヤールの硬貨を、ポケットに突っ込んでいた。
朝の4時50分、まだ夜も明けきらぬ7月のテヘラン空港、街が目覚めるまではと、ガランとした待合室で待つ私に、少年が近づいてきた。
日本でいえば小学校の五・六年生といったところであろうか、こんなに早くから靴磨きの仕事である。
料金は5000リヤールというが、つい先ほど初めてイランのお金を手にした私、それが高いのやら安いのやら。けれど、飛行機から下りたばかりの靴、いずれにせよ靴磨きはいらない。
ノオと断ってはいたが、こんなに朝早くから頑張る少年に、飴の一つでもといった気持ちで、両替したお金の中の、一番大きな硬貨を渡そうとしたのである。
少年は冷たく首を振って、静かに私を見ていた。きっと桁外れに少な過ぎたのだろう。けれど、何だかそこに、そうではないイラン社会の誇りに、襟を正されたような思いを感じてしまう。
そんな気まずさの残った、待合室の木の椅子に寝転がって待つこと2時間、ようやく街も騒がしくなってきた7時過ぎ、タクシーの勧誘に来た男の、街中まで5ドルという値段を、インフォーメーションで聞いた4ドルに値切って、空港を出た。
てっきり彼がドライバーかと思っていたら、私を別の男に引きあわせて去って行く。
「ホメイニ広場、4ドル」もう一度確認して乗り込んだタクシーだったが、動き出してまもなくスピードをゆるめたドライバー、ふり返って5ドルと言い出す。まったく何を言うかとインドを思い出してしまう。
そういえば街の様子もインドに似ている。この道路の混雑などは、まさにインドそのもの。イランとインドとは、全然別の文化圏のように思っていたが、むしろ、共通点の方が、多いのかもしれない。ひょっとして、近代国家の成立する以前は、同じ文化圏といえたのだろうか。
その混雑にリクシャの姿が見えないのは、少々寂しくもあったけれど、隙間が少しでもあれば容赦なく突っ込んでくる車は、インドをほうふつとさせ、なんだかワクワクするものを感じてしまう。
横断歩道も、歩行者には信号など意味がない。赤だろうが、青だろうが、車の間を縫ってどんどん渡る。ついつい踏み出せない私など、通り合わせた子供の渡るのをこれ幸いと便乗して、横を小走りに渡ること度々であった。
 |
| インドに負けないこの混雑、通りを渡るには気合がいる。 【テヘラン、エマーム・ホメイニ広場近く】 |
そんな道を、タクシーは突っ走る。ガンとして4ドルと言い張っていると、途中女性を一人乗せた。少々稼ぎを増やそうというわけだろう。まあ、スペースは十分あるので、文句はいわずにそのままで。
けれど彼女が下りてまもなく、ポリスに止められてしまう。しぶしぶタクシーを出た彼、何かをさかんにアピールしていたが、舌打ちをしながら帰ってきて、渡された紙切れを私に見せて嘆いた。
言葉の意味はわからなかったけれど、どうも、罰金か何かのようだ。別にスピードを出し過ぎているというわけでもなかったのだから、いわゆる白タクだったのだろうか。それとも、外人を乗せるのに特別の許可でもいるというのか。
運の悪い彼、しばらく走ってまた止められてしまう。彼は先ほどの用紙を見せ、さかんに今度も言い訳をしているようであったが、またまたもう一枚用紙を渡され、頭を抱えて戻って来た。いやにポリスが幅を利かせている。
その彼、ホメイニ広場で約束の4ドルを渡し下りようとすると、その紙を私に見せ、もう1ドルくれと、泣き出さんばかりに訴えてきた。その表情から察すると、赤字だと言わんばかりに。けれど私のせいではない。気の毒ではあったが、かたくなに拒否してリュックを担いだ。
ところがその私も、車でごった返すホメイニ広場のロータリーを抜け、アミーレ通りに向かおうとすると、ポリスに呼び止められてしまう。
あの嘆いていたドライバーを思い出し、何かを言われるのかと少々いぶかしく思いながら彼の質問に耳を傾けると、英語でどこに泊るのかと聞く。
私はガイドブックにあったエコノミークラスのホテルを言ってみると、近くのシー・カザーホテルが、インターナショナルで設備も良くお勧めだと、地図を示して教えてくれる。どうも、職務上の質問かと思ったのだが、ただの外人への興味のようだ。
そんな興味を持つのは彼ばかりではなかった。街を歩いていると、やたら英語で話し掛けられる。10歳程の子供から、60歳は越えているだろうと思える大人まで。中には通りすがりのバスの窓から「ハロー!」と大きく叫んでいく人もいる。
子供相手なら、「やあ」と笑って通り過ぎても、年配の人にまじめな顔で呼び止められると、何なんだろうと立ち止まって聞き入ってしまう。
けれどたいがいは、「名前は?」「国は?」「いつ来た?」「イランをどう思う?」「仕事は?」といったこと。知っている限りの英語を総動員して楽しんでいる。英語を話すということが、ちょっとしたステータスででもあるのだろうか。
だんだん面倒になって、少々の声は聞こえなかったふりをしてさっさと歩く。けれど3人に1人くらいは返事を返す。それでも受け答えのしっぱなしのように思えてしまう。
街角で地図でも広げていようものなら、知らぬ間に人の輪に囲まれている。みんなとても親切、とても親日的。
 |
イランの人達は、驚くほど親切、それにとても親日的。 |
そんな一人が私に言った。「アメリカはダメ。日本は良い。」
バンダル・アッバースまでの列車の切符を買いに行って立ち寄った、サンドイッチレストラン。歳のころは、30半ばくらいだろうか。
「何故アメリカはダメ?」そう聞いてみた。
「アメリカはフセインをけしかけて、イランを攻めさせた。フセインはその褒美がもらえなかったから、クェートに攻めた。」それが彼の答えであった。
えっ!と思ってしまう。8年にも及ぶ戦争を戦い抜いた彼ら、フセインの背後にアメリカの影を見ていたのだろうか。
とはいえ、はたしてそれが事実かどうなのか、私にはかいもく見当のつかぬところ。けれど、彼の反米感情だけは、容易にぬぐえない、確かな事実と言ってもよさそうであった。
「で、日本は何故良いの?」
私は、てっきり、日本の経済力とか、イランとの友好関係が返ってくるのかと思った。
「アメリカと戦った国だから」それが彼の答えであった。
えっ、えっ!と思ってしまう。喜んでよいのやら、悲しむべきなのやら。
勿論、旅の間で、そんな意見を聞いたのは、彼だけであった。けれどすっかり生まれ変わったと思っている日本だが、外から見れば、必ずしもそうではないようだ。
いや、いや、ひょっとして、変わったように思い込んではいるけれど、あの日本が今と違うのは、単に歴史のどこかでの、ちょっとしたボタンのかけ違いだけなのだろうか。
 |
テヘランの西、アーサーディー広場に、ペルシャ建国2500年を記念して建てられた、高さ45mのタワー。現代イランの象徴的モニュメント。 |






















































