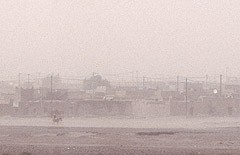「こらぁっ〜!」
もう日本語である。猛ダッシュで坂を駆け上る。といっても、背と胸に大小のリュックを背負っている身。猛ダッシュは気持ちだけ。勝負は初めから決まったようなもの。逃げる彼の後ろ姿は、次の角で足のみになり、その次では音のみとなってしまう。
その昔、敵の侵入を防ぐため、わざと迷路のようにしたというモロッコのスーク、昨日着いたばかりの異邦人は、息をはずませ、悔しさをかみしめるよりすべがない。
私の剣幕に驚いていた、通りがかりの老人の、何か言いたそうな顔を残して、モロッコの海の玄関、タンジェの町は、早朝の静けさに戻っていた。
昨日、スペインの港町アルヘシラスを出た船が、ジブラルタル海峡を渡って我々を降ろしたここモロッコは、ちょうどラマダーンの最中であった。
夕方、明日の列車の確認もかねて出かけた駅で、日の沈むのを待って入った食堂は、客よりも自分達の食事をまず急ぐのか、なかなか人が出てこない。
 |
おそらく、コカコーラと読むのでしょう。味は同じでも、なんとなく気分は違って…(マラケシュのホテルのテラスにて) |
聞くところによると、午後の6時がブレックファストだという。9時にもう一度食べ、深夜の1時に3度目を食べるという。結局ラマダンといえども、3度食事をするのである。ただそれが日没後に集中するだけだ。
これでは眠る時間もなく、昼間はおそらくボーッとしてしまうのではないだろうか。そう言えばここタンジェは、ガイド攻勢が凄まじく、もうここでモロッコがいやになってしまう人も多いというのに、港に着いた時は拍子抜けするほどもの静かであった。ひょっとしてそれは、このラマダンのおかげだったのだろうか。
そんなことを思ってはいたが、今朝7時半、まだ薄暗く人気のないスークの中を、駅へと歩いていた私に、この男が近づいてきた時は、やはりおいでなすったかと身構えた。
タンジェを案内しようというのだが、駅に向かっているのは見ればわかりそうなもの。「ノー」とつれなく断って、坂道を急いでいると、なにやら言いながら横にならんで歩いていた彼が、少し歩みを遅らせて、後ろに回ったかと思うと、ひょいと私の帽子をひったくって逃げたではないか。
「このやろう!」朝のスークにこだまする怒りの声。尻に火がついたようにスピードを加え逃げ去る彼。それにしても悔しい。まさか帽子にくるとは思ってもいなかった。
私には愛着のある帽子ではあっても、売ってお金になるような代物ではない。何か生活に困ってというより、遊びでやっているようで、よけい腹が立ってくる。
誰かに喜ばれて大事にされるのならまだしも、もう洗濯もされずに、そこらに捨てられるのかと思うと、なんだか立ち去りがたい名残惜しさを感じて……。
列車の切符はカサブランカまでしか買えず、2等で114ディラハム(12ドル)。ところがすべてコンパートメントで、座席も座り心地の良いソファー。日本の列車に慣れていると、コンパートメントは何故かデラックスに感じて、1等ではないのかと心配してしまう。
そんなコンパートメントに同席した2人の女性は、モロッコ語は勿論のこと、アラブ語、フランス語、スペイン語を話すという。英語は苦手だといいつつ、どうしてどうして、上手なものである。モロッコでは彼女のように何ヶ国語も自由に操る人に多く出会った。驚きである。
列車が動き出すとまもなく、ジュラバ姿の男が入って来た。ジュラバというのは三角のフードのついた袖以外は足首まで筒状に着るモロッコの服で、これを着るとちょうど「ゲゲゲの鬼太郎」の「ねずみ男」のような姿になり、フードで頭を覆うと誰が誰だかわからなくなってしまう。
そんな彼が、私に話し掛けてきた。なにげない会話から次第に話は次の町アシラの話に。アシラを見てからその切符で夜行に乗れば、明日の朝にはマラケシュに着ける。ここまで来てアシラに寄らない手はない、アシラで下りれば良い所に案内すると、誘うことしきり。
私は帽子事件の直後でもあって、彼の話に心動かされることなく、「ノー」を言い続けていると、アシラ近くで出て行った。
 |
ジュラバを着て、フードをかぶると、人相風体がわからなくなる。ゲゲゲの鬼太郎に出てくる、ねずみ男を思い出してしまう。 |
やや心配そうに黙って私の方をちらちら見ていた隣の女性は、彼の出て行ったのを確認すると、「あの人よく喋ったね」と、少し安堵の表情を向けた。
後でガイドブックを読んでみると、タンジェのみならず、アシラにも要注意との投稿が載っていた。実際のところはわからないが、荷物も持たず、特急に乗って、さかんに初対面の旅人を誘っておいて、一駅で降りていくというのも妙な話である。うっかり誘いに乗っていたら、いいカモにされていたかもしれない。
私が迷うことなく断れたのは、帽子事件のおかげである。なんだか帽子が最後に、次に迫る危機の警告を残していってくれたように思えてしまう。あの帽子、何処でどうしていることか。