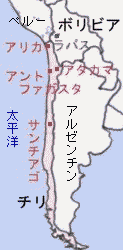
空軍のロケット砲の後を受けて、モネダ宮殿に突入した先鋒隊が、奥の大統領執務室で見たのもは、血にまみれたアジェンデの死体であった。
ピノチェト率いるクーデター軍の包囲攻撃の中、降伏を拒否したアジェンデは、ラジオを通して悲痛なる別れをチリ国民に残し、自ら命を絶った。1973年9月11日午後のことである。
「サルバドール・アジェンデ」、その名が世界を駆け巡ったのは、ちょうどその3年前、1970年10月、日本ではまだ70年安保の熱が冷めやらぬ秋であった。
「世界ではじめて、選挙によるマルクス主義政権の誕生」期待と危惧、双方の目が、南アメリカ、アンデスの西に細長くへばりつく共和国、チリに向けられた。
それから3年、急激な改革は、国民を賛否両極へと分裂させ、その緊張が、チリ経済の機能を麻痺させる。物不足が深刻化し、事態はにっちもさっちも行かなくなってしまった。
良くも悪くも、こういった事態を切り抜けるのは独裁である。いつの世も、形はどうであれ、何らかの独裁、何らかの全体主義が、こういったのっぴきならぬ混乱では要求される。
マルクスがプロレタリア独裁を唱えたのは、的を射た分析といえよう。もっとも、そんな状態になる前に、適切な舵取りをすべきであると私は思うのであるが、ともあれ、ここチリで、その独裁を買って出たのは、ピノチェト率いる軍隊であった。
その後約16年間、1990年に民政に移行するまで、チリの人々はその軍政の下で暮らすことになる。
つい最近、その彼がスペイン判事の要請によって、イギリスで入院中に逮捕され、本国に返還するのしないので、再び世界の注目を浴びたのを、覚えておられる方も多いことであろう。
彼の軍政下で犠牲になった死者は、3000人にのぼるというが、一説には2万人を上回るとも言われている。
 |
5月のサンチアゴ、街を歩いていると、時々スペインを歩いているような錯覚に陥ってしまう。 |
今朝、30時間を越える日本からの長旅の末、やっとチリに着いた私は、宿を求めてコロニアル風の建物が立ち並ぶ旧市街を歩いていた。
ちょうど日本の晩秋を思わせるサンチアゴの五月、人々はセーターに上着といった出で立ちで、さっそうと歩いている。
足の長い人が多く、彼らにまじって歩いていると、サンチアゴの街は、まるでスペインの何処かを歩いているような錯覚に陥ってしまう。
かつて人々を、アジェンデ支持に駆り立てた貧困は、ここを歩いている限り姿を消したようだ。軍政下での多くの弾圧にもかかわらず、経済を立て直した人として、ピノチェトへの評価が、ここチリで賛否二分されているというのも、うなずける思いであった。
そんな人々の喧騒の中、悲劇の舞台モネダ宮殿は、ビルの谷間で身の丈を低くし、静かに沈黙を守っていた。まるで浮き沈みする人の世を、しっかりと見つめる錨のように。
 |
ビルに囲まれて、静かにたたずむモネダ宮殿。当時は警察もほとんどが軍側についた。 |
宿は訪ね歩くこと4件目で、やっと何とか気に入ったホテルを見つけることが出来た。リュックを背負ってほぼ旧市街を、北から南に縦断したことになる。
一泊いくらかと問えば、ドスミルと返ってきた。2,000ペソ。何かいやに安いような気がしたが、寝不足でもうろうとした頭、ピンとこない。まあ安い分にはいいかと、決めたのだが、念のためにメモに書いてもらったら、12,000とある。ドシシエントミルだったのだ。
「えっ、これはいくらになるのだ?」
いっこうに頭が回ってくれない。
怪訝そうに見つめる宿の女将の視線を感じつつ、メモ用紙でもたもたと計算してやっと、25ドル程度かと見当がついた。まあ、相場のようである。
 |
サンフランシクコ教会の裏通り。趣のある石畳にコロニアル風の建物が並ぶ。一泊ドスシエントミルで泊まったホテルはこの一角。 |
部屋で荷を解いて時計を見れば、目の奥に綿が詰められたような眠気にもかかわらず、まだ4時であった。ここで眠っては昼夜のペースをチリ型にあわせることは出来ないと、もう少し我慢すべく街に出ることにした。
まずは街の中心、アルマス広場に出てから、ぶらりと博物館に回ったのであるが、博物館はもう閉まっていた。さてどうしたものかとうろうろしていると、ポルノ映画館に出くわした。
ポルノなら目がぱっちりだろう。何もチリ初日にこんな所に直行しなくてもと思いつつ私は、入場料の1,400ペソ(2.8ドル)を払っていた。
チリのポルノはラテンの国にもかかわらず、日本よりソフト――だと思う。というのも、席に座ったとたん、どうやら眠ってしまったらしく、実はよく覚えていない。
気がついたら7時を回っていて、まぶたは鉛のように重たい。まだチリに来て十時間、治安事情も良くわからないサンチアゴの映画館で居眠りなどしていては、何が起きるか分からない。
私は上着の下のカメラを確認しつつ、あわてて宿に帰った。ホテルでは、バタンキュウと眠ってしまう。
翌朝、6時半、壮快な目覚め。さて、本日の予定はとガイドブックを見ようとした所、見当たらない。何処にも。何処にも。
確か昨日、宿を探している時はあった。博物館を探している時もあった。けれど何処にもない。何処にも???
これはえらいことです!

























