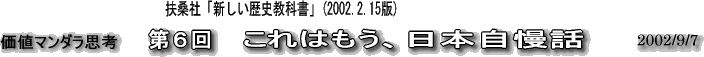
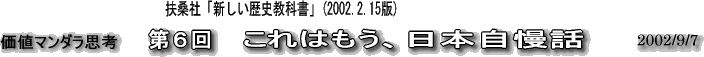
価値マンダラ思考 第6回 これはもう、日本自慢話 2002/9/7
扶桑社「新しい歴史教科書」 ― 2002.2.15 版 より ―
2002年8月15日、愛媛県教育委員会は、来春開校する県立高中一貫教育校3校での扶桑社版「新しい歴史教科書」の採用を決定し、再びこの教科書が全国の関心を集めた。全国的には、採用率ゼロに等しいこの教科書の、何処がそんなに問題なのか。710円で教科書を買って、私の視点で読んでみた。
| 注 | テキストは 扶桑社「新しい歴史教科書 (2002年2月15日発行)」 を使用。文中(P)はその教科書のページ数を示す。 |
扶桑社の「新しい歴史教科書」は、序章の「歴史を学ぶとは」で次のように述べている。この教科書の基本姿勢が要約されているので、少々長くなるが、後半の全文を紹介しよう。
「……けれども、そういう事実をいくら正確に並べても。それは年代記といって、いまだに歴史ではない。いったいかくかくの事件がなぜおこったのか、誰が死亡したためにどういう影響が生じたかを考えるようになって、初めて歴史の心が動きだすといっていい。
しかしそうなると、人によって民族によって、時代によって、考え方や感じ方によってそれぞれまったく異なってくるので、これが事実だと簡単に一つの事実をくっきり描き出すことは難しいということに気がつくであろう。
ジョーウジ・ワシントンは、アメリカがイギリスから独立戦争で独立を勝ち得たときの総司令官であり、合衆国の初代大統領であった。アメリカにとっては建国の偉人である。しかし戦争に敗れアメリカという植民地を失ったイギリスにとっては、必ずしも偉人ではない。イギリスの歴史教科書には、今でもワシントンの名前が書かれていないものや、独立軍が反乱軍として扱われているものもある。
歴史は民族によって、それぞれ異なって当然かもしれない。国の数だけ歴史があっても、少しも不思議ではないのかもしれない。個人によっても、時代によっても、歴史は動き、一定ではない。しかしそうなると、気持ちが落ち着かず、不安定であろう。だが、だからこそ歴史を学ぶのだともいえる。
歴史を固定的に、動かないもののように考えるのはやめよう。歴史に善悪を当てはめ、現在の道徳で裁く裁判の場にするのはやめよう。歴史を自由な、とらわれのない目で眺め、数多くの見方を重ねて、じっくり事実を確かめるようにしよう。そうすれば、おのずと歴史の面白さが心に伝わってくるだろう。」(P7)
「我々の若い頃は……」そんな言葉で始まる話を、もし貴方がある程度年配なら、一つや二つは口にしたことがあるだろう。また、もし貴方が若者なら、一つや二つは、聞かされたことがあるのではないだろうか。どういうわけか、話す方は楽しげに、けれど聞かされる方はうんざりと。
というのも、この手の話は、過去の事を話してはいるものの、語っているのはそればかりではないのである。実はその語り手は、過去の出来事を話すと同時に、それを経てきた自分を讃えているのである、自分の値打ちを。まあ早い話が、自慢話なのである。
我々と過去の出来事は、単に年代記として語られている限りは、感情的に切り離されてはいるけれど、そこに、誰が、何故、何の為に、そしてその結果は、などといった背景の意味を含めると、その過去の出来事は、今の貴方の思いを代弁する物語へと変貌する、「我々の若い頃は…」の話が、話し手を讃える話であったように。
だから異なる価値観の人は、一つの事実を、互いに違った意味の中に見ることになる。価値観が異なれば、その価値観で組み上げた歴史像も異なる。つまり年代記では万国共通でも、歴史となると、それは難しい。
「歴史は民族によって、それぞれ異なって当然かもしれない。国の数だけ歴史があっても、少しも不思議ではないのかもしれない。個人によっても…」その通りであろう。
「しかしそうなると、気持ちが落ち着かず、不安定であろう。だが、だからこそ歴史を学ぶのだともいえる。」ん?…だが、だから…?歴史を学ぶのは、気持ちを落ち着かせるため?今まで明晰であった著者の論理展開が、どういうわけか、ここで急に不明瞭になってしまう。
私の経験ではこんな場合、おうおうに論の展開にごまかしがあるのだが、どうやら少々唐突とも思える次の呼びかけに、持っていきたかったようである。「歴史に善悪を当てはめ、現在の道徳で裁く裁判の場にするのはやめよう。」と。
なんだかこれが言いたくて、もっともな理屈を並べていたようにも見えるのであるが、かんぐりは止めとして、果たしてそうであろうか。
確かに「死者に鞭打つようなことは止めよう」と言うのなら、言いたいことはわからぬでもないが、歴史は価値観によって異なるということから、善悪を含めた判断を停止しようというのなら、ちょっとお門違いと言いたくなる。
何故なら、この教科書の著者も言うように、歴史は、判断を含まない年代記ではなく、その人が、その国が、その民族が、その出来事をどのように考えるかという、立場の表明でもあるのだから。
過去の出来事を、今の貴方がどう考えるかということは、死者を鞭打つことではない。それは、今の貴方の人格を規定することなのである。それは民族の今のありようを、国家の今のありようを、規定することなのである。
例えば、悪事を働いた人間が、数ヵ月後にひょっこり顔を出し、「過去の出来事に善悪を当てはめ、裁くのはやめよう」などといえるだろうか。例え会社などで、社長の世代が代わっていても、それをどう考えるかは、過去ではなく、現在の貴方がどういう人かという問題なのである。
昨今のニュースで知らされる不祥事に対して、いっこうに責任の所在や、判断の誤りをはっきりさせようとしない、日本社会の体質と共通するものがあるように思える。
ところが、この教科書は、裁判の場にするのはやめようと言いつつ、実は、しっかりと裁判の場にしているのである。年代記でなく、歴史を書くと言っている以上、当然のことであるが、その法廷で、著者は、〈日本の無罪〉を宣言する。ではその判決を見てみることにしよう。
この教科書を読み進むと、やたらギネスブック的お国自慢が目につく。古代のところで少し拾ってみると、序章の所では、紀元後の歴史を20cmの物差しに当てはめて、次のようにいう。
「…日本が欧米を知って以来の歴史を、歴史のすべてだと思ったら、大きな間違いをおかすことになる。日本の歴史がいかに長、く豊かであるか、かえってここからはっきり分かってくるはずだ。明治からさかのぼって、……『源氏物語』書かれたのは10cmのころである。皆さんは聖徳太子の名前を知っているだろう。5cm9mmで登場する。その頃ヨーロッパは、まだ存在しない。フランスやドイツやイタリアがはっきり姿をあらわすのは12〜13cmで、日本でいえば鎌倉時代である。……」(P9)
〈あれっ、ローマはイタリアではなかったっけ。それに、ギリシャやエジプトや中国やインドはどうなっているのだ。〉と突っ込みを入れるのは止めにしておこう。明らかにこの表現が意図する日本像は、日本の相対的位置ではなく、〈何と日本は古くからの国だろう〉という感情である。
「…かつて土器のルーツといわれた西アジア(メソパタミア)の壷は、最古のものでも約9000年前である。それに対し、日本列島では、1万6500年前にさかのぼる土器が発見され、現在のところ世界最古である。…」(P24)〈何と世界最古の文化だぞ!〉
「…けれど日本語は現在、地球上で話されている人口数で、7番目の大きな位置をしめる言語である。……」(p30)〈日本語は。日本だけでしか話されていないけれど、それでも世界で7番目、どうだ立派だろう!〉
「…日本最大の大仙古墳の底辺部は、エジプトでも最大のフク王のピラミッドや秦の始皇帝の墳墓の底部よりも大きかった。……」(P35)〈なに、ピラミッドは古墳より2000年以上古い?ダメダメそんな所を比較しては。別に意味がなくてもいい、日本のほうが勝る点はないのか!底辺部の大きさ、おお、それがいい、それでいこう。〉
なんだか、世界最古の文明をもち、わが国の天皇は、エジプトの王や秦の始皇帝よりえらかったみたい。そんな気分になりませんか。またこんな表現もある。
「……といった山の幸。それに豊富な貝類。このように比較的、食料に恵まれていたので、日本列島の住人は、すぐには大規模な農耕を開始する必要がなかった。……」(P24)〈『…大規模の農耕は発展しなかった。』と書けば日本が遅れていたみたいだから、出来る能力はあったのだがやらなかったというニュアンスにしておこう。〉そんな声が聞こえてきそうな。
詳しくは資料なり、直接教科書を見ていただきたいのだが、この教科書では、日本の歴史の始まりを、〈大きいこと古いことは良い事だ〉という素朴な感情に訴え、とても立派なイメージにしたいようである。
この遠い昔は、「超過去」とでも名付けようか、過去を語っているようで、語っているのは実は、現在の自分達の値打ちなのである。王や英雄が自分達の存在を特別なものとするために、生き証人のいない数世代先の先祖を神だとする話は、どこの国でもよくある話である。同じような心理なのだろう。
ここでまず日本の歴史を展開するはじめが確定される。〈日本はもともと立派だったのだ〉と。
古代編で繰る返されるギネスブック的賛美は、次第に「わが国」という概念を、混沌から切り離し、歴史を担う実体へと、イメージをつくり上げていく。そして、律令国家のところでは、誇らしげに次のように語られている。
「…わが国は、中国から謙虚に文明を学びはするが、決して服従はしない―――これが、その後もずっと変わらない、古代日本の基本姿勢となった。そのかわりに、わが国は学ぶときにはどこまでも徹底して学ぶ。……」(P45)
「謙虚に」「徹底した」と、感情を込め述べられている賛美の主語は、「わが国は」なのである。「聖徳太子の時代の人は」ではない。よろこんでいただきたい、この教科書を学んでいる貴方も、自慢話の側に組することが出来るのである。
明らかにこの文は歴史の記述ではなく、「われわれは…」に始まる、アジテーションと言えよう。
ところでその「わが国」とはいったいどのようなものだろう。
「…こうして豪族たちの個別の立場を離れて、天皇を中心に国家全体の発展をはかる方針がようやく確立することになった。」(P53)
大化の改新後壬申の乱を経て確立した体制をそう評価する。さりげない表現であるが、天皇中心であることが、私利私欲の対概念として提示される。ここで示された「わが国」観は、天皇が政治の後方に退く武家の時代によりいっそう弁護する形であらわれる。
「…頼朝は朝廷の承認を受けて、地方の国ごとに……」(P84)
「…しかし、将軍が天皇から任命されてその地位につくという原則に、変更はなかった。」(P97)
「…天皇の権威を頼りのしている。それが武家の権力の限界だった。」(P108)
「…頼朝が全国の武士から頭として心服された背景には、頼朝自身の指導者としての力量のほかに、清和天皇の血統を受け継いでいた源氏出身という要素も影響した。」(P108)
〈歴代の武家たちも、自分では決断できなかった。常に、天皇の許しを請うてきた〉とでも言いたいのだろう。
そして現代、 「…国歌『君が代』の君は日本国憲法のもとでは、日本国および日本国民統合の象徴と定められる天皇をさし、この国歌は天皇に象徴されるわが国の末永い繁栄と平和を祈念したものと解釈されている。」(P187)
この教科書によると歴史の主体「わが国」とは、君が代の歌のように、〈君の繁栄こそ私の願い〉というように、天皇を精神的権威の頂点にして、没我的に結ばれあった集団なのである。
それが良いとか悪いとかは別にして、自我を独立させている人と、集団に融合させている人とでは、その集団への態度は変わったものとなってくる。自我を独立させていると、その集団への批判は冷静に聞くことが出来ても、融合させていると、一緒になって腹が立つ。
例えば、精神基盤を別の所に置いていると、会社の隠蔽する不正の告発もいとはないが、会社人間だと、一緒になって不正の上塗りをする。
日本史の見方においても、例えば彼の自我を、ある宗教に置いていたとすると、日本史の出来事に関して、好悪どちらも冷静に受け止めることが出来る(―――もっとも己の宗教となると、話は別かもしれないけれど)。
けれどこの教科書の史観のように、歴史の主人公を有機体としての「わが国」として、その集団に没我的に融合してしまうと、わが国への批判は、許しがたい己への批判となり、わが国の失態は、我慢ならない己の失態になる。結果、あの手この手の必死の弁護が展開される。
例えば、好ましくないことは、好ましいことと併記され、帳消しが企てられる。
「…日朝修好条約が結ばれた。これは朝鮮側に不平等な条約だったが、長らく懸案であった朝鮮との国交が樹立した。」(P200)
「…天皇暗殺を計画したとして、幸徳秋水などを逮捕し、翌年、死刑にした。他方で、政府は工場法を制定し、労働者保護に努めたが、充分ではなかった。……」(P229)
「…共産党やその支援者を取りしまる治安維持法を制定した。しかし、合法的な社会主義政党の活動はさかんで、1928年に行われた初めての普通選挙では、これらの政党からも代議士が生まれた。」(P257)
「…これまでの歴史で、戦争して、非武装の人々に対する殺害や虐待をいっさいおかさなかった国はなく、日本も例外ではない。日本軍も、戦争中に進攻した地域で、捕虜となった敵国の兵士や民間人に対して不当な殺害や虐待を行った。一方、多くの日本の兵士や民間人も犠牲になった。例えば、第二次大戦末期、ソ連は満州に侵入し、日本の一般民の殺害や略奪、暴行を繰り返した上、捕虜を含む約60万人を………」(P288)
またそれが無理でも、天皇の権威だけは守らねばならない。そこが「わが国」なるものの権威の最後の拠り所なのだから。
曰く 「…天皇は立憲君主として、政府や軍の指導者が決定したことに介入すべきではないという考えから、意に反して、それらを認められる場合もあった。ただ、天皇ご自身の考えを強く表明し、事態を収めた事が2度あった。一つは1936(昭和11)年の二・二六事件の時であった。
………もう一つは、1945(昭和20)年8月、終戦の時であった。ポツダム宣言を受諾するか否かで、政府や軍首脳の間で意見がわかれ、聖断(天皇がくだす判断)を求められた天皇は、『これ以上戦争を続けることはできないと思う。たとえ自分の身がどうなっても、ポツダム宣言は受諾すべきである』と述べ、戦争は終結した。……」(P306)
〈悪いことは意に反して、良いことは意に添って〉なんとも都合のよいことで。
「…1943年11月、この地域の代表を東京に集めて大東亜会議を開催した、会議では、各国の自主独立、各国の提携のよる経済発展、人種差別の撤廃をうたう大東亜共同宣言が発せられ、日本の戦争理念が明らかにされた。…」(P280)
「…これに対し、戦争中、日本によって訓練されたインドネシアの軍隊が中心となって独立戦争を開始し、1949年独立を達成した。……インドでは……ビルマは……これらの地域では、戦前より独立に向けた動きがあったが、その中で日本軍の南方進出は、アジア諸国が独立を早める一つのきっかけとなった。」(P282)
〈なーんだ、日本て結構良いことしてるじゃん〉そんな若者達の声が聞こえてきそうな。そうなんだよ。
「GHQは、新聞、雑誌、ラジオ、映画を通して、日本の戦争がいかに不当なものであったか宣伝した。こうした宣伝は、東京裁判とならんで、日本人の自国の戦争に達する罪悪感をつちかい、戦後日本人の歴史の見方に影響を与えた。」(P295)
ついにわが国の戦争への反省は、GHQが戦争が不当であると宣伝した為のもので、あたかも根拠のないデマゴギーのようになってしまう。
ここに「歴史に善悪を当てはめ、現在の道徳で裁く裁判の場にするのはやめよう。」という著者の言葉の真意がお分かりだろう。それは、〈日本の戦争行為を糾弾するな〉ということなのである。この歴史書で無罪放免を言い渡す為に。
以上、この教科書は、歴史を語ることによって、どんな貴方であることを望んでいるのであろう。それは〈 日本の威厳こそ価値の根源 〉 と感じる貴方である。そのために、虚像も恐れずわが国の像をつくりあげる。そして、その一員であると貴方をおだてる。
「…そうすれば、おのずと歴史の面白さが心に伝わってくるだろう。」 そう、日本が威張っていられれば、貴方も威張っていられるのだから。この史観の甘い誘惑である。しかしその気分の良さは、あの「我々の若い頃は…」で始まる自慢話を語るときの気分と同じである。誰かの悪口で、その場が盛り上がる時の愉快さに似る。誰しも心のどこかに覚えがあるだけに不気味でもある。
では、この史観から、どのような明日への指針が、導き出されるであろう。
「…クウェートから撤退させた(湾岸戦争)。この戦争では、日本は憲法上の理由により軍事行動には参加せず、巨額の財政援助によって大きな貢献をしたが、国際社会はそれを評価しなかった。このため国内では、日本の国際貢献のあり方について深刻な議論がおきた。…」(P314)
もし古代の所の論調なら、『わが国の財政援助は世界一であった』と誇らしく書く所であるが、なんとも批判的である。それもそのはず、大事なのは、平和への支援ではなく評判なのだから。大事なのは「わが国」の威厳なのだから。
この史観が行き渡れば、「わが国の威厳を守るため」という考えの下、平和や、民主主義や、人権が、徐々に制限され、或いは、その威厳の危機に際しては、容易に崩されるだろうことは、いうまでもないだろう。
以上私は、この教科書の採用には反対である。若者を裸の王様にはしたくない。