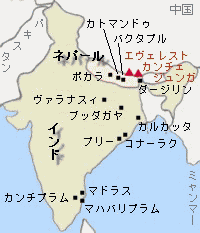
彼は両手の平を上に向け、首を振っている。汗ばんだ浅黒い顔の奥で、さも困ったような目がこちらを見ている。おつりの10ルピー(30円程度)が無いというのである。
2月といえども、日本の真夏を思わせるカルカッタの暑さが、ようやく峠を越えた、夕暮れのシアルダー駅前、19時15分発の列車、ダージリンメールには、まだ充分の時間がある。
私はため息を装いながら、そのタクシー運転手を見つめていた。歳の頃は50前といったところか。
前回のインドの旅の初めでは、こういったやり取りが、その汗ばんだ肌のように、不快に感じて、「だめ、40ルピーと言ったではないか」と、きっと声を尖らせていたことであろう。
けれど私はなんだか、「じゃんけん、じゃんけん…」と言い合って、お互い勝負の気持ちを盛り上げる時のような、そんな空気の張りを、むしろ面白くさえ感じていた。
というのも、日本からの機内では、同席した聞き上手の学生さんに、さんざん前回の旅で経験したインドの渾沌を、得意になって話していたのだが、いざカルカッタに下りて見ると、「あれっ、ここ本当にインド?」と思えるほど、普通なのである。
 |
道端の共同井戸では、洗濯したり、体を洗ったり、2月といえどもカルカッタは日本の真夏の暑さ。 |
確かに、物乞いはいたけれど、まあ、他の国でも見かける程度と、そう大差はない。その上、旅行者にまとわりつく自称ガイドや物売りも、いるにはいるが、覚悟していた程の迫力がない。それに、街が予想外に綺麗なのである。
あのインドだからと気合を入れてやってきたのに、なんだか拍子抜けしてしまう。どこか違うなと感じつつ、地下鉄を降り、カリー寺院へと歩いていた次の日、ハッと気がついた。
牛がいないのである、神なる牛が。その分、道路に糞を残すということもなく、街の印象があか抜けしている。
「カルカッタは、ずいぶんきれいな街だ」と、この時期日本の学生さんでにぎわう、ホテル街サダル・ストリートで出会った若者に言ったところ、「ええっ、これで!」と驚かれてしまった。
はたして、インドが変わったのか、私が変わったのか、それともカルカッタが特別なのか、いずれにせよ私は、カルカッタの普通ぶりに、この分では旅も楽そうだと安堵しつつも、なんだか、ビールから苦味が抜けたようで、少々物足りなさを感じていたのである。
 |
朝のごみ収集作業。カルカッタはけっこうさっぱりしているように、私には思えました。 |
"やっぱりインドはこうでなくては!" 何とか10ルピー多くせしめようという彼を前に、私も困ったような顔を向けつつ、じゃあ、チョキでいくかグーでいくかと、次の一手に思いを巡らせていた。
ものごとを、ある程度外から、前後を含めて見ることが出来るということは、事の成り行きを、そのストーリーにダブらせて理解することの出来る体験を、心の引き出しに持っているということであろうか。
再読するサスペンス小説には、初めの時に味わった、主人公になりきってのハラハラドキドキはないものの、そのときには味わえなかった、作者の工夫の面白さや、構成の妙に気づかされることがあるもの。私は人生の後半の楽しさも、そんなところにあるような気がしている。
だから、確かに健康でありたいとは思うけれど、若さにこだわることよりも、老に向かって進むことに、むしろ興味さえ覚えている。いったい何処まで、前半で着込んだこだわりを脱いだ自由を、遊べるようになれるのかと。
もっともこれは、あがいてもどうしようもない諦めも、混ざってはいるのだろうけれど。
そんな老獪の楽しさを気取って、30円(10ルピー)をめぐっての、おじさん二人の攻防が続く。
「だったら、持ち合わせの30ルピーで…」
実のところ私も、ポケットを探せば、40ルピーの都合はついたであろう。けれど、つり銭が無いと言う彼に乗じて、10ルピー値切ってやろうと頑張ってみる。
気前のいい日本人の、「じゃ、釣りはいいや」という声を期待していたようだが、そうはいかない。ところが敵もさるもの、次の手が用意されていた。
ダッシュボードの小物入れを開けると、そこに1枚放り込まれていた、しわくちゃの5ルピー札を、おもむろに取り出し、これしかないから、釣りをこの5ルピーにまけろと差し出す。思わず口元がほころんでしまう。なるほどなるほど、そこまで用意していたとは。
ところが、さてどうしたものかと、思案する私の目の下に、チラッと映った、彼の丸く膨れた胸のポケットからは、なんと、なんと、お札の束が、無造作に顔をのぞかせているではないか。頭かくして尻かくさずの愉快さ。
ゲームオーバー、私の勝ち! 私はふきだすのをこらえながら、ゆっくりと、そして歌舞伎役者のように少々オーバーに、人差し指を彼の胸ポケットに向けた。
「オーッ」 悪びれるでもなく、しょげるでもなく、気後れするでもなく、それまでの会話などまったくなかったかのように彼は、明るくお釣りの10ルピーを差し出した。
苦笑苦笑! 30円の攻防。何故か憎めないインドの人々。
 |
踊るシバ神。カルカッタインド博物館。見ていると、何だか気持ちが愉快になってくるような…。 |



