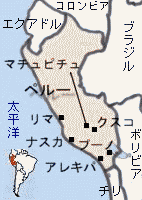
「それじゃあ、お気をつけて」
そう言うと彼女は、張りつめた気持ちの私を残して、シアトル空港の人ごみの中へと消えた。彼女にとってここはホームタウン、そのリラックスした後ろ姿がうらやましい。
成田から同席した彼女は、シアトル在住の奥さんで、一年ぶりの里帰りだったとのこと。主人もカメラ好きだとかで、私のコンタックスT2を見て、主人のと同じだと話が弾んだ。
その彼女、南米は恐ろしいですというのである。何でも、つい最近のニュースで、気が付いたらホテルのバスタブに寝かされていて、内臓が切り取られていたというのを聞いたという。
切り口には応急の手当てがされており、病院の電話番号と電話が近くに置かれていて、何とか命は取り留めたそうであるが、それを聞いて震え上がったという。その他にも、ブレスレッドを盗るために手首ごと切り取ったという話もあるという。
私は特別仏教徒というわけではないが、何故か仏教の伝統を持つ国というのはなじみやすい。また、旅をして、イスラムの国というのも、少しはなじみになった。けれど南米はまだ未体験であった。
良かれ悪しかれ、初体験を前にしては、想像が膨らむもの。それでなくても銃撃戦の末、リマの日本大使公邸での人質事件が解決されたのは、まだ記憶に新しい。不安はさらに膨らんでしまう。
何事も土俵に上がる前の不安というのは厄介なものだ。いざ上がってしまえば、取り組む相手が具体化し、必ずしもうまく行くとは限らないとしても、一つ一つ切り崩す糸口が見つかるものだ。
けれど想像で膨れ上がる不安というのは、はなから全体を気力で押し返さねばならない。これが結構しんどい。
私は成田の待合室で知り合ったペルー人の家族を待った。彼らとは何もない成田の待合室で8時間も一緒に時間をつぶした仲である。
というのも、私は名古屋から成田乗継で来たのだが、案内のままに進んだら、名古屋で出国してしまい、成田ではすでに国外の人となってしまっていた。
そんなわけで、空港を出ることが出来ず、朝の10時から夕方の6時まで、彼らと私だけのガランとした待合室で、ひたすら時間のたつのを待ったのであった。その彼らもペルーへ行きますと言ったら、開口一番、気をつけてくださいと言うのであった。
心配そうな顔をすると、街中での鞄の持ち方などいろいろ注意を教えてくれた。その上心配だから、空港からホテルまでのタクシーをつかまえてくれるという。有り難いやら、よけい不安になるやらではあったが、とりあえず見失わないようにしなければ。
このシアトル空港は乗り継ぎであったけれど、米国では一度入国しなければならないということで、手続きのカウンターに並んだ。
やっと終わって出てくると、ただの案内人だと思っていた別の係官に、突然、所持金を聞かれた。とっさに答えた私は、金額を一桁多く間違えてしまう。二三歩進んでから間違いと気づいて言い直してももうダメ、申告組みの列に並ばされ、変更を許してもらえない。
私の番がきて、その旨を係官に告げたのだが、しっかり荷物を調べられ、乗り継ぎの時間に間に合うかヒヤヒヤさせられてしまう。
 |
リマの街は、太平洋に面した断崖の上、砂浜の上には海岸道路が走る。どんよりとはしていたが、雨はほとんどないという。 |
それからどれくらい乗ったであろう。シアトルからマイアミへと乗り継いで、ペルーの空港に着いたのは、まだ朝も明け切らぬ早朝であった。それにしても長かった。
日本からの無調整の時計は20時を指している。名古屋を出てから12時間ということはないから、もう一回りして36時間ということか。
乗り継ぎのよい便というのも考えようによっては問題である。連絡が悪いと、仕方なくホテルで一泊という事になるのだが、トントンと乗り継いでくるとかなりの時間狭い機内に閉じ込められてしまう。内蔵がまだフワフワと空を飛んでいるようであった。
空港の外には彼らの迎えの車が来ていた。久しぶりの再開なのだろう、抱き合って喜び合っている。その彼らの車に私も便乗させてもらって、リマの街に向かった。
途中車を止めてタクシーを拾ってくれた彼は、ここまでのタクシー代かわりにと差し出したお礼を受け取ろうともせず、もしも何かあったら連絡してくださいと、住所と電話番号のメモを渡してくれた。
 |
店のガードマン。野球のバットを持って立っていた。その姿は、まじめな顔とはうらはらに、少々ユウモラス。 |
お守りのようにそれを握りしめ、さていよいよ一人になったかと緊張する私を乗せたタクシーは、リマの南、ミラフローレス地区のオスタルラルコの前で止まった。
ところがラルコの正面は前面鉄格子が下ろされ、ひっそりと人気もない。あたりをうろうろしたあげく、営業していないのかと思い立ち去ろうとしたら、私を見かねたそのタクシーの運転手は、わざわざ降りてきて、呼び鈴でホテルの人を呼び出してくれた。
どうやらホテルといえども間口が開け放たれているとは限らないらしい。中から人が出てくるのを見ると運転手は、笑顔で私に別れを告げ去って行った。その人なつっこい表情に私は、ことのほか緊張している自分がなんだか滑稽に思えてくる。
 |
よく見れば、どこにでもある普通の街。やたら緊張している自分が滑稽に…。 |
旅をして実際に接してみると、どこの国の人達も、皆いい人達だ。どうして人と人が、戦争するほど憎みあうことが出来るのか、不思議なくらいだ。私の旅はそんな人の親切に乗っかって成り立っているといっても過言ではない。
勿論そんな中に混じって、ごくわずかにキツイ人達がいる。しかも彼らは旅人を狙って近づいてくるから、数は少なくても出会う確率は無視できないものとなってしまう。だから油断は出来ないのだけれど、この地球上それがどこでも、決して怪物の国を旅しているわけではないのである。
次第に輪郭を際立たせ始めたリマの実際を前にして、今までの得体の知れない不安は、まるで闇にうごめく魑魅魍魎が、朝日とともに消え去るように、目の前の景色から姿を消し始めていた。
ひょっとして人の恐怖や偏見は、この実体のない魑魅魍魎を相手にしているのかもしれない。






































